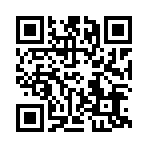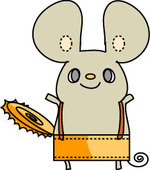高校野球&ドラフト会議
2010年10月29日
昨日はプロ野球のドラフト会議でした。
愛するタイガースはクジ運がなく、またしても1位指名ではずれです。
11年連続とか、、、、
さて、野球といえば、近江八幡市の高校野球の名門「八商」が秋の県大会で安定した投手力、守備力で優勝しました。
滋賀県第1代表として近畿大会に出場。
1回戦に勝利して、ベスト8で春の甲子園出場が有力と思っていたのですが、、
現実には、1回戦で奈良県第2代表の天理高校に1対9で敗戦です。
あんなに堅実だった守備の乱れで、エラーで失点を重ねてしまいました。
でも、1年生の投手が素晴らしいピッチングをしていますから、来年の夏の甲子園が楽しみです。
(とらきち)
愛するタイガースはクジ運がなく、またしても1位指名ではずれです。
11年連続とか、、、、
さて、野球といえば、近江八幡市の高校野球の名門「八商」が秋の県大会で安定した投手力、守備力で優勝しました。
滋賀県第1代表として近畿大会に出場。
1回戦に勝利して、ベスト8で春の甲子園出場が有力と思っていたのですが、、
現実には、1回戦で奈良県第2代表の天理高校に1対9で敗戦です。
あんなに堅実だった守備の乱れで、エラーで失点を重ねてしまいました。
でも、1年生の投手が素晴らしいピッチングをしていますから、来年の夏の甲子園が楽しみです。
(とらきち)
ひこねば2010市民活動まつり(彦根市)
2010年10月28日
今回で4回目となるひこねば2010市民活動まつり。今年のテーマは『輝け!市民のチカラ』
飲食コーナー、体験コーナー、お楽しみコーナーと種類を分け、地産地消を目指す、こだわりの手作り品の販売や足つぼマッサージ、バルーンアートやミニフリマなど。聖泉大学校舎内では学びのフリーマーケットと称する街の学校を開催。子どもも大人も自分の興味に合わせて学びたいことを学べる企画。“チンドン屋から広がる世界”“不思議な国モロッコ”などわくわくするような講座ばかり。
日時:2010年11月20日(土)、21日(日) 10:00~17:00
場所:聖泉大学・短期大学部
主催:ひこね市民活動センター
後援:彦根市
問合せ:彦根市金亀町7-5 ヴォーリーズ洋館
tel 0749-24-4461
fax 0749-47-5402
e-mail hikone.cac@gmail.com

飲食コーナー、体験コーナー、お楽しみコーナーと種類を分け、地産地消を目指す、こだわりの手作り品の販売や足つぼマッサージ、バルーンアートやミニフリマなど。聖泉大学校舎内では学びのフリーマーケットと称する街の学校を開催。子どもも大人も自分の興味に合わせて学びたいことを学べる企画。“チンドン屋から広がる世界”“不思議な国モロッコ”などわくわくするような講座ばかり。
日時:2010年11月20日(土)、21日(日) 10:00~17:00
場所:聖泉大学・短期大学部
主催:ひこね市民活動センター
後援:彦根市
問合せ:彦根市金亀町7-5 ヴォーリーズ洋館
tel 0749-24-4461
fax 0749-47-5402
e-mail hikone.cac@gmail.com
伝えるコツを身につけよう
2010年10月27日
NPOのための広報スキルアップセミナー
会報やチラシ、ポスター、ホームページなど、もっとうまく作るにはどうすればいいんだろう?
このセミナーは、株式会社電通と特定非営利活動法人日本NPOセンターの協力のもと、
広報力の向上を目的としたスキルアップセミナーです。
「幅広く情報を伝えたい!」「人をたくさん集客したい!」と、広報の方法で困っている人はいませんか?
チラシやポスターなど、広報での「伝える」コツをお教えします。
NPOに限らず、一般の方や企業で広報を担当されている方にもオススメです。


【日 時】 2010年11月13日(土)
10:00~15:30(受付開始9:30)
【会 場】 近江八幡市総合福祉センターひまわり館 2階研修室
【講 師】 池田 佳代さん(特定非営利活動法人OurPlanet-TV理事)
【定 員】 50名(先着順)
【参加費】 1,000円(資料代など)
■プログラム
9:30~ 受付開始
10:00~12:00 午前の部
12:00~13:00 休憩
13:00~15:30 午後の部
【主催】 NPO法人 近江八幡市中間支援センター
【協力】 株式会社 電通、特定非営利活動法人 日本NPOセンター
【お申込&お問い合せ先】
NPO法人 近江八幡市中間支援センター
TEL:0748-36-5570 FAX:0748-36-5553
e-mail:chukan@npo-omi8man.com
※お申込については、電話・FAX・メールで受け付けております。
※定員は申込先着順となります。
たくさんの方のご参加をお待ちしております。
会報やチラシ、ポスター、ホームページなど、もっとうまく作るにはどうすればいいんだろう?
このセミナーは、株式会社電通と特定非営利活動法人日本NPOセンターの協力のもと、
広報力の向上を目的としたスキルアップセミナーです。
「幅広く情報を伝えたい!」「人をたくさん集客したい!」と、広報の方法で困っている人はいませんか?
チラシやポスターなど、広報での「伝える」コツをお教えします。
NPOに限らず、一般の方や企業で広報を担当されている方にもオススメです。


【日 時】 2010年11月13日(土)
10:00~15:30(受付開始9:30)
【会 場】 近江八幡市総合福祉センターひまわり館 2階研修室
【講 師】 池田 佳代さん(特定非営利活動法人OurPlanet-TV理事)
【定 員】 50名(先着順)
【参加費】 1,000円(資料代など)
■プログラム
9:30~ 受付開始
10:00~12:00 午前の部
12:00~13:00 休憩
13:00~15:30 午後の部
【主催】 NPO法人 近江八幡市中間支援センター
【協力】 株式会社 電通、特定非営利活動法人 日本NPOセンター
【お申込&お問い合せ先】
NPO法人 近江八幡市中間支援センター
TEL:0748-36-5570 FAX:0748-36-5553
e-mail:chukan@npo-omi8man.com
※お申込については、電話・FAX・メールで受け付けております。
※定員は申込先着順となります。
たくさんの方のご参加をお待ちしております。
酒蔵工房の講座があります♪
2010年10月26日
八幡山の間伐竹を使って、色々なもの作り体験が出来ますよ
●竹紙漉き講座
日 時 11月8,9,10、11日 午後2時~4時
場 所 酒蔵工房(近江八幡仲屋町元1)
費 用 A4サイズ 1枚200円
内 容 八幡山整備間伐竹リサイクルの竹繊維を使って竹紙の素材を作っています。間伐竹紙漉きを体験します。(環境省支援事業・協働 八幡山の景観を良くする会)
●竹染め講座
日 時 11月16、17,18,19日 午後2時~4時
場 所 酒蔵工房(近江八幡仲屋町元1)
費 用 ハンカチ800円 スカーフ1500円(素材 コットン)
内 容 八幡山間伐竹の生葉を使い、オレンジ・イエロー・ブラウンの模様染めを体験します。
(環境省支援事業・協力 八景会)
●竹自転車を作る講座
日 時 第1回 10月23日(土) *終了済
第2回 10月30日(土) 午前10時~午後4時
第3回・第4回 未定
場 所 酒蔵工房(近江八幡仲屋町元1)
費 用 茶菓代 300円
内 容 八幡山整備の間伐竹を使って、竹自転車を作ります。自転車のバスケットを作ります。
(環境省支援事業・協働 東洋竹工・エコリサイクル・八景会)
お申込み・お問い合わせ
八幡酒蔵工房 担当:小関
TEL 0748-32-6421 FAX 0748-32-6421
e-mail delfee@yahoo.co.jp

●竹紙漉き講座
日 時 11月8,9,10、11日 午後2時~4時
場 所 酒蔵工房(近江八幡仲屋町元1)
費 用 A4サイズ 1枚200円
内 容 八幡山整備間伐竹リサイクルの竹繊維を使って竹紙の素材を作っています。間伐竹紙漉きを体験します。(環境省支援事業・協働 八幡山の景観を良くする会)
●竹染め講座
日 時 11月16、17,18,19日 午後2時~4時
場 所 酒蔵工房(近江八幡仲屋町元1)
費 用 ハンカチ800円 スカーフ1500円(素材 コットン)
内 容 八幡山間伐竹の生葉を使い、オレンジ・イエロー・ブラウンの模様染めを体験します。
(環境省支援事業・協力 八景会)
●竹自転車を作る講座
日 時 第1回 10月23日(土) *終了済
第2回 10月30日(土) 午前10時~午後4時
第3回・第4回 未定
場 所 酒蔵工房(近江八幡仲屋町元1)
費 用 茶菓代 300円
内 容 八幡山整備の間伐竹を使って、竹自転車を作ります。自転車のバスケットを作ります。
(環境省支援事業・協働 東洋竹工・エコリサイクル・八景会)
お申込み・お問い合わせ
八幡酒蔵工房 担当:小関
TEL 0748-32-6421 FAX 0748-32-6421
e-mail delfee@yahoo.co.jp
沖島影絵発表会
2010年10月26日
ようやくアップできました~!!
ブログの更新に手間取っている鈴木ですm(__)m
アサヒアートフェスティバルAAF学校in沖島が開催され、10月17日の日曜日は影絵の発表会でした。
前日、子供たちが作った影絵がどんなお話になっているのでしょうか?
楽しみですね~
(前日の作成風景は、前回のブログをご覧ください☆)
さて、2日目の今日は、まずご飯を頂き、(前日と同じく、沖島で取れた魚がふんだんに使われたお弁当です)
影絵の作成をする親子さんたちは、影絵の発表の準備。
島外から、影絵の見学に来られた方は、島の探索をして、その後発表会の見学となっています。
沖島散策をしたことがない私は、沖島散策に同行させていただきました
今回、ガイドをして下さった中島さんです

中島さんは、現在は八幡市内にお住まいですが、沖島出身で、島の事とってもお詳しいです。

参加者の皆さんです。
沖島が好きで、ちょくちょく沖島に来れているというご夫婦、アートが好きで今回の機会に沖島まで足を延ばしてみたという方、そしてパリからお越しの方(!)、アサヒアートのスタッフの方、ボランティアの方と一緒に島の散策に出かけました。
昔は、コミュニティセンター前まで埋め立てられていて、メイン道路が現在と違うとのこと。

まず、昔のメイン道路を進みます。

ハイキングコースもあるそうなのですが、今のシーズンは蜂が出るとのことで今回は断念。
昔のメイン道路、めっちゃ狭いです!!
さすが、車のない沖島。
そのまま進むと、昔の小学校跡へ。

小学校跡へ続く階段です。
そこを出て、海岸沿いを歩き、資料館を見学。
その後、お寺や神社、さらに細いろじ「めじ」をとおり、島を一周
約2時間で一回りしてしまいました
周りには音がなく、とても静か。
「ここは湖の上って不思議・・・」
まさにそんな感じです。
普段はいけない沖島の場所が散策で来て、みなさん大満足☆
「来てよかった~」って、全員の方がおっしゃっていました
さてさて、そして、影絵の発表会です。

今回のアーティストさん、こやのてつろうさんを見つけたのでパチリ
2日間で仕上げるのは大変やった~とのこと。
いやいや、期待していますよ~☆
会場には、40人ほどのお客様で満席!!
立っている方もおられました。
まず、アサヒのおねえさんのご挨拶を聞き、影絵の発表会の始まり始まり。

ある日、島の子供たち3人が遊んでいると、なにやら異変が・・・

島にイノシシがやってきたのです(昔はいなかったイノシシが、最近沖島に上陸したとのこと)

亀がやってきて、なにやら異変が起きていると伝えます。(沖島は、対岸からみると亀の形に見えるそう)

そして、一人の子の魂がオジロワシに連れて行かれてしまいます。(オジロワシは沖島でよくみられる鳥)

2人が追いかけると、そこは35年前の沖島・・・

このままでは、沖島の多様な生物が失われてしまうと言われ…。
2日間で作られたとは思えない、お話でした!
子供たちも一生懸命影絵を動かしてくれていて、それが伝わり、とてもよい作品になっていました。

島で取れた竹を使って、ウロツテノヤ子バヤンガンズのお兄さんがこんな楽器を演奏していました。
とってもバリの雰囲気☆

イノシシや亀、オジロワシを始め、たくさんの沖島の生物が劇中には登場します。
沖島の貴重な資源の発掘、文化の発信。
子供たちにも、私たちにもとてもよかったのではないかなぁと思いました。
私は、「今日沖島に来てよかった」というお声が聞けたことが嬉しかったです。
これからも沖島が熱いですよ!!
今後の動きにも大注目です☆
最後に、帰りの船から見た夕日です
ぜひぜひ、ご自身の目で沖島の素晴らしさを見てくださいね~。

ブログの更新に手間取っている鈴木ですm(__)m
アサヒアートフェスティバルAAF学校in沖島が開催され、10月17日の日曜日は影絵の発表会でした。
前日、子供たちが作った影絵がどんなお話になっているのでしょうか?
楽しみですね~
(前日の作成風景は、前回のブログをご覧ください☆)
さて、2日目の今日は、まずご飯を頂き、(前日と同じく、沖島で取れた魚がふんだんに使われたお弁当です)
影絵の作成をする親子さんたちは、影絵の発表の準備。
島外から、影絵の見学に来られた方は、島の探索をして、その後発表会の見学となっています。
沖島散策をしたことがない私は、沖島散策に同行させていただきました
今回、ガイドをして下さった中島さんです

中島さんは、現在は八幡市内にお住まいですが、沖島出身で、島の事とってもお詳しいです。

参加者の皆さんです。
沖島が好きで、ちょくちょく沖島に来れているというご夫婦、アートが好きで今回の機会に沖島まで足を延ばしてみたという方、そしてパリからお越しの方(!)、アサヒアートのスタッフの方、ボランティアの方と一緒に島の散策に出かけました。
昔は、コミュニティセンター前まで埋め立てられていて、メイン道路が現在と違うとのこと。

まず、昔のメイン道路を進みます。

ハイキングコースもあるそうなのですが、今のシーズンは蜂が出るとのことで今回は断念。
昔のメイン道路、めっちゃ狭いです!!
さすが、車のない沖島。
そのまま進むと、昔の小学校跡へ。

小学校跡へ続く階段です。
そこを出て、海岸沿いを歩き、資料館を見学。
その後、お寺や神社、さらに細いろじ「めじ」をとおり、島を一周
約2時間で一回りしてしまいました
周りには音がなく、とても静か。
「ここは湖の上って不思議・・・」
まさにそんな感じです。
普段はいけない沖島の場所が散策で来て、みなさん大満足☆
「来てよかった~」って、全員の方がおっしゃっていました
さてさて、そして、影絵の発表会です。

今回のアーティストさん、こやのてつろうさんを見つけたのでパチリ
2日間で仕上げるのは大変やった~とのこと。
いやいや、期待していますよ~☆
会場には、40人ほどのお客様で満席!!
立っている方もおられました。
まず、アサヒのおねえさんのご挨拶を聞き、影絵の発表会の始まり始まり。

ある日、島の子供たち3人が遊んでいると、なにやら異変が・・・

島にイノシシがやってきたのです(昔はいなかったイノシシが、最近沖島に上陸したとのこと)

亀がやってきて、なにやら異変が起きていると伝えます。(沖島は、対岸からみると亀の形に見えるそう)

そして、一人の子の魂がオジロワシに連れて行かれてしまいます。(オジロワシは沖島でよくみられる鳥)

2人が追いかけると、そこは35年前の沖島・・・

このままでは、沖島の多様な生物が失われてしまうと言われ…。
2日間で作られたとは思えない、お話でした!
子供たちも一生懸命影絵を動かしてくれていて、それが伝わり、とてもよい作品になっていました。

島で取れた竹を使って、ウロツテノヤ子バヤンガンズのお兄さんがこんな楽器を演奏していました。
とってもバリの雰囲気☆

イノシシや亀、オジロワシを始め、たくさんの沖島の生物が劇中には登場します。
沖島の貴重な資源の発掘、文化の発信。
子供たちにも、私たちにもとてもよかったのではないかなぁと思いました。
私は、「今日沖島に来てよかった」というお声が聞けたことが嬉しかったです。
これからも沖島が熱いですよ!!
今後の動きにも大注目です☆
最後に、帰りの船から見た夕日です
ぜひぜひ、ご自身の目で沖島の素晴らしさを見てくださいね~。